「日本一たらこを大切にする会社」としてたらこの魅力と可能性を追求、地域貢献と雇用創出にも繋げていきたい。【株式会社ヤマトバイオレッツ/大野城市仲畑】

株式会社ヤマトバイオレッツ 代表取締役 梁川剛一。
株式会社ヤマトバイオレッツは、2013年9月に株式会社ふくや子会社として設立した、明太子の一次原料(塩たらこ)生産加工・食品(明太子)OEM受託工場です。明太子の製造において国際基準規格「ISO22000」に準じた工場で、お客様に更なる安心・信頼をお届けできるよう、原料の選定から商品の企画・開発・製造・品質管理まで一貫して行っています。
「日本一たらこを大切にする会社。一粒も無駄にしない。すべてを価値あるものとすることをスローガンに掲げ、さまざまな取組を続けており、特にごみ減量・リサイクル活動に関しては大野城市より優良企業として表彰されました。
たらこ・明太子の可能性を追求し、持続可能な産業化を目指している社長の梁川 剛一(やながわごういち)氏に、品質管理体制の取組や新ブランド「たらこ食堂」立ち上げの背景、今後のビジョンなどをお聞きしました。
株式会社ヤマトバイオレッツはどのような会社ですか?歴史や事業内容についてお聞かせください。

1987年、明太子の一次原料(塩たらこ)の生産加工会社として株式会社ヤマトを創業しました。その後2013年に「味の明太子ふくや」の子会社を設立、社名を「株式会社ヤマトバイオレッツ」へ変更しました。ふくやが販売する辛子明太子の原料となる「塩たらこ」の製造をはじめ、たらこを使った新しい商品の開発などに取り組んでいます。福岡博多の地で30年にわたり塩たらこ・明太子を手がけていますので、明太子づくりに関してはかなりのこだわりがあります。
塩たらこと明太子はどう違うのですか?

そうですね、まず一般的に「たらこ」というのは、スケトウダラの卵巣(魚卵)を塩漬けにしたものを指します。魚卵を見たことはありますか?ふぐの白子などもそうですが、魚の卵って非常に柔らかいんです。その柔らかいスケトウダラの卵をタルの中に入れ、回転させながら塩漬けにします。この工程を「塩蔵」といい、だいたい一晩タルを回転させると、粒が立ってプチプチとした弾力性が出てきます。これが「塩たらこ」ですね。この塩たらこを唐辛子の入った調味液に漬け込んだものが「辛子明太子」です。つまり塩たらこが一次工程、辛子明太子が二次工程ということですね。
当社では現在、仕入れの3割程度の塩たらこをふくやに納品し、7割で食品OEM(明太子)委託製造を行っています。
「ISO22000」の認証を取得されていますが、品質管理体制の具体的な取り組み内容を教えてください。
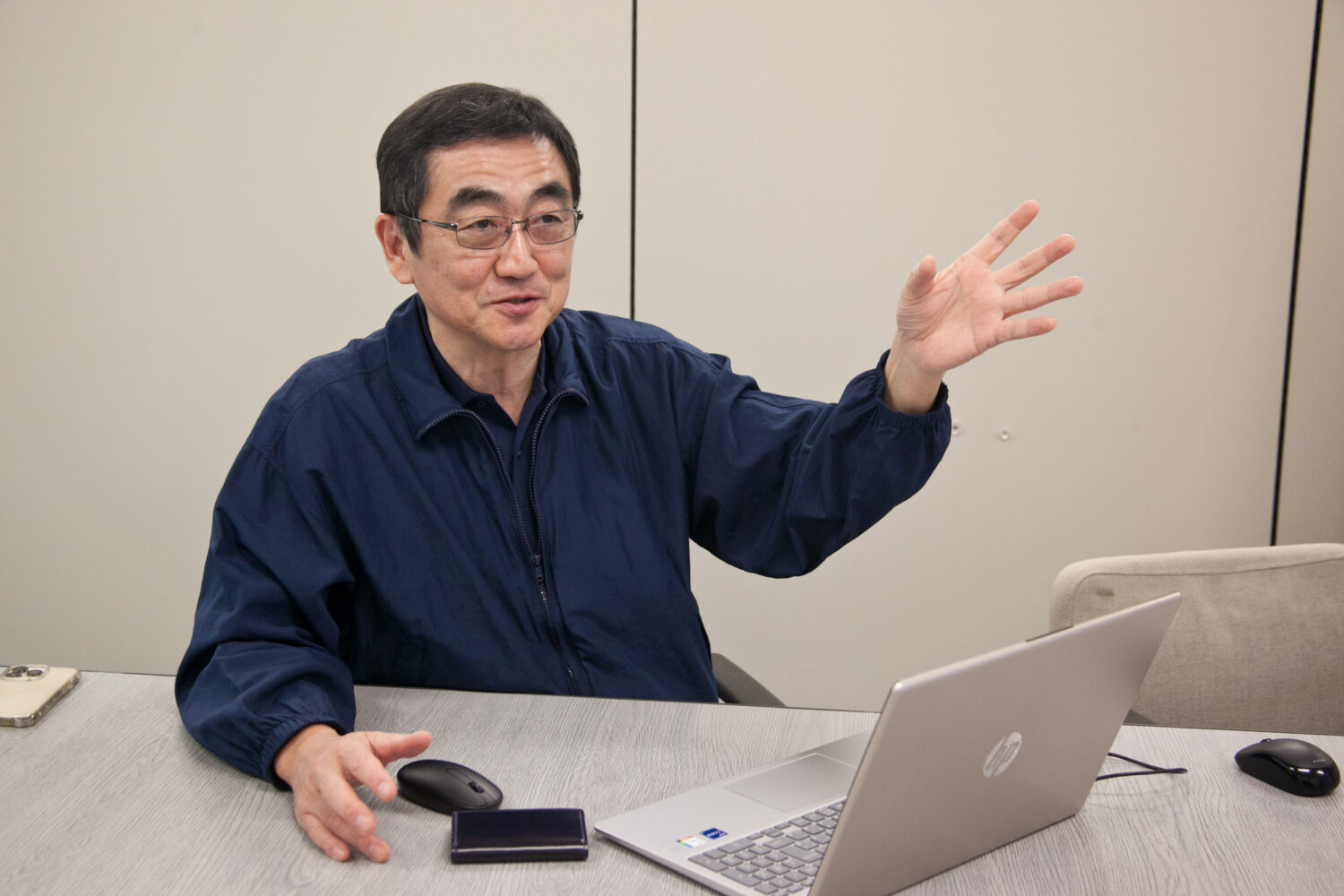
まずISO22000を取得する目的は、国際規格に基づいた食品安全マネジメントシステムを組織全体で構築・運用し、食品の安全を確保することです。HACCP(ハサップ)と異なるのは、基本的な衛生管理や具体的なリスク管理、問題発生時の対応がマネジメントシステムとして追加されている点です。
食品の製造工程において、各プロセスの危害分析を行い、予想される被害の重要度に応じてきちんと手を打っていくことが必要となります。特に大事なのは食品の安全性を確保するために管理すべきチェックポイント、これをCCP(クリティカルコントロールポイント)といいます。通常ですと加熱して微生物を死滅させるのですが、当社の場合は冷蔵品なので、特に温度管理は徹底して行います。
あとは亜硝酸ナトリウムですね。これはいくらやたらこなどの魚卵加工品、ハム、ウィンナーなどの食肉加工品に発色剤として使われます。亜硝酸根残存量は、1kgに対して5ppm以下と法律で定められていますので、それは絶対遵守しないといけません。当社では亜硝酸の分量を守るためCCP(クリティカルコントロールポイント)に設定して管理しています。
こういう流れをきっちり決めて、記録ををしっかり取って、ちゃんと検証していく。こういう大きなPDCAサイクルを回していくのが食品安全マネジメントシステムです。
「ISO22000」を取得してから社内の意識は変わりましたか?

変わりましたね。良くなりました。
小さい会社ですから、みんなで話し合って会社の方針などを決めていくんですけど、ISO22000の食品安全基準というのはさまざまな規格がきっちり定められているんですよ。その定められたことを従業員一人一人がしっかり守ることによって、会社が有効に機能していきます。それがわかると、皆が自立的に動いてくれるようになりました。
またISO22000の認証を維持するためには、年に一度は認証機関の審査員により監査をうけ、合格する必要があります。ちょうど今その時期なので、審査員が来るまでに内部監査ということで、自分たちで監査をしあっています。できているところとできていないところを出して、それをきちんと修正して、自分たちがどれくらいできているのかをいうことを年に一回確認します。つまり、会社のトップマネジメント以外の基準があって、それについて従業員たちが考えて動いてくれるようになったということですね。
実は私はISOの審査員もやっていて、ISO9001、ISO22000。
それとHACCP、FSSCの審査員の資格を持っています。
製造工程における環境への配慮や資源の有効活用について、どのような取り組みをされていますか?

やはり食品廃棄物をなるべく出さない、出た分については有効利用していくということを心がけています。例えばたらこを製造加工するとどうしてもカスやくずが出るので、これらは全て動物性残滓として家畜の飼料にしています。それが年間8.8トンになります。また再資源化するダンボールは年間7.4トン、プラスチック類は年間8.4トンになります。これらはリサイクル業者へ渡し、再資源化を図っています。この活動が認められ、令和4年度にごみ減量・リサイクル優良事業所として大野城市から表彰されました。
OEM食品委託製造に採用しているCAS冷凍について教えてください。

CAS(Cells Alive System)冷凍とは、細胞組織を壊さずに凍結する技術です。食材の鮮度や風味、栄養価を保つ効果があり、食品の長期保存や品質向上に役立っています。
冷凍庫でギリギリ凍らない程度に冷やした水やお茶に衝撃を与えると、端からぶわぁ〜っと凍っていく現象を見たことがありませんか?それと同じ原理で、急速冷凍装置にCASエンジンを組み合わせてぐ〜っと冷やしていって、−40℃近くになるとある瞬間バッと凍るんです。細胞膜を壊さずに凍結できるため、解凍してもドリップが出ないんです。
このCAS冷凍を使って作ったのが「星の粒」という商品です。漁船から腹だし(採卵)した原卵を最短ルートで仕入れ、塩蔵から味付けまで一気に行ってCAS冷凍をしました。近海子らしく一粒一粒は非常にちいさな粒ですが、ピンと粒がたって引き締まった感じで、舌の上で心地よく弾むのが特徴です。
CAS冷凍の技術により、たらこの長期保存かつ鮮度維持が可能になり、より良い商品をお客様に届けることができるようになると同時に、食品ロスにも繋がると考えております。
「たらこ食堂」ブランドを立ち上げた背景と目的を教えてください。

ジャパンクオリティにこだわったすべてがプレミアムな「たらこ」の新星『星の粒』
ヤマトバイオレッツという社名だけではなかなか商品を世に広めることが難しくて、製品をちゃんとブランド化していく必要があると考えました。商品の良さでやっていくためには、ぶれないように、まず商品の世界観をブランドとして先に固めたかったんです。
例えば昔のデパートの食堂のように、お父さんはカレー、お母さんはパスタ、誰々は和定食みたいにいろんなものが食べられる、みんながいろんな食べ方ができるようなたらこのブランドを作りたい。そうしてできたのが「たらこ食堂」です。
「たらこ食堂」サイト:https://taracosyokudo.jp/
「たらこ食堂」オンラインショップ:https://taracosyokudo.stores.jp/
「たらこ食堂」ではいろいろな商品を開発・販売していますね。「たらコルネ」とはどんな商品ですか?

『たらコルネ』(チーズ・うに・海苔)
「たらコルネ」とは、天然物のたらこの中に海苔・チーズ・うにのソースを注入した商品です。たらこの形状を損なわない独自の技術で、端から端までぎっしりソースを注入しているので、どこを食べてもたらことソースのハーモニーが楽しめるようになっています。たらコルネの海苔は、2025年1月にジャパン・フード・セレクションにおいて最高賞のグランプリを受賞しました。
この商品を作ったのは、たらこをもっと多くの人に食べてもらいたいなと思ったときに、小さな子どもやご年配の方には辛子明太子はちょっと辛すぎるなと。なんとかできないかと考えていくと、辛子明太子はそもそも、たらこの韓国風の食べ方なんですね。だとすると、フランス風やイタリア風、日本風のたらこがあってもいいんじゃないかって思いまして。昔からご飯のお供に欠かせない海苔とたらこを掛け合わせたらもっと美味しくなるんじゃないかと思って、試行錯誤を繰り返して完成したのがこのたらコルネです。チーズやウニもたらこに合います。たらこの可能性をもっと広めるために、例えば各都道府県の名産と掛け合わせても面白いんじゃないですかね。沖縄の島豆腐や宮崎のマンゴーなど、試してみたいですね。
すっぴんたらこも人気商品だそうですが。

辛子明太子の常識を覆す当社自慢の逸品『すっぴんたらこ』
そうですね、“すっぴんたらこ”は化学調味料・亜硝酸・合成着色料を一切使用せずに作りました。添加物を使ってないとたらこが色落ちしていくんですよ。亜硝酸を使った辛子明太子は綺麗な色をしています。でも無添加を望むお客様にとっては、色落ちしても構わない、それが自然だと喜ばれるんですね。味に関しても、今では無添加の醤油や味醂やお出汁があるので、非常に美味しく作れます。無添加にすることの一番のネックは“粒感”なんですよ。添加物を使わずに粒感を出そうとすると大変難しい。最終的に2年間ほどかけて色々な塩を試して、ヒマラヤのレッド岩塩に落ち着きました。多くのミネラル分が良い作用になっているんでしょうね、粒感を出すことができたんです。ただすごく濃い飽和食塩水に漬け込むので、塩抜きをしないと辛くて食べられません。そこでも数の子の塩抜きに着想を得て、味も粒感も損なわないように2段階に分けて塩を抜いていきます。
たらこ本来の美味しさを追求した、完全無添加のすっぴんたらこは当社自慢の逸品です。
外国人雇用にも力を入れているようですが、雇用を進めていく中で苦労された点や工夫されたことはありますか?
外国の方を雇用するには、支援機関を通す必要がありますが、当社は自社で支援機関を内製化しています。通常は支援機関が人材を募集して面接して、雇用が決まった後は定期的にヒアリングしたりするなど、外国人と支援機関とが結びついてから入社して来るんですけど、何か問題が起こったときに、私たちももっとしっかり外国人とコミュニケーションを取りたいなと思うようになりまして。
それならもう自社で外国の送り出し機関と直接やり取りして、面接して採用して、出入国管理法なども全部行って、公私共に密な関係を築くことができるようになりました。密になった分、大変なこともありますけど、お互いに意見を出し合いながら信頼し合えるようになったと思います。
家を出て街を出て国を出て、ここに来る子たちはみんな一生懸命です。もうバイタリティが違いますね。仕事に対する考え方やルールなども教えればちゃんと覚えるし、自分で考えて動いてくれるのであまり苦労する点はないですね。
そもそも外国人を雇用しようと思ったきっかけはなんですか?
日本人の雇用が難しくなってきたからですね。
この先、日本の人口がどんどん減っていくのに雇用は少なくなる一方で、じゃあどうするかっていうと、外国人のリーダーを作らないといけないんです。外国人を雇用するだけではなく、特定技能2号になってもらって、中間管理職になってもらうということは、もう次の課題として早い段階から計画に入っています。けっこう長期的なスパンで考えているんですよ。
ですから今働いている外国人の方たちも、置き換えができる単純な労働者という風には捉えていません。だいたい5年くらいしたら本国に帰ってしまうんですけど、だからこそずっと一緒にここで働きたいなと思ってもらえるようにならないといけません。当社を選んでもらうしかありませんから。だからこそ公私に渡ってコミュニケーションをしっかり取っていくことに重点を置いています。
何名くらいの外国人が働いているのですか?

今は19名です。ベトナムの方が多いですね。ネパールの方も1人います。
社員全体の1/3が海外の方です。
自社で支援機関を兼ねるのはけっこう大変なんですよ。銀行口座を開くのにも1人分で半日かかります。スマホの開設や電気ガス水道の手配なども全部やります。生活のことも仕事のことも全部やりますから、他の支援機関を通すよりも濃い関係になりますよね。そんな中でやっぱりずっと働きたいって言ってもらえるからやりがいがあるんですけどね。
最後に、御社が目指す今後のビジョンや目標についてお聞かせください。

当社は「日本一たらこを大切にする会社。一粒も無駄にしない。すべてを価値あるものとする」ことをビジョンとして掲げています。日本一たらこを大切にするというのはどういうことかというと、たらこの命を大切にするということです。たらこが持つ可能性や魅力をしっかり見て、製品化してお客様に届けていきたい。
たらこを切り売りして安く売るんじゃなくて、きちんと付加価値をつけた商品を適正価格で売っていきたいですね。「稼ぐ力」なくして自立なし、です。
親会社のふくやはずっと根幹に地域貢献が根づいているんですよ。もうそこは全然ぶれていない。だからふくやが利益を出すと、地域貢献に繋がる、地域に還元されていきます。ふくやを通じて、私たちももっと地域に貢献していきたいと考えております。
●代表取締役 梁川剛一
1994年4月、株式会社ふくやに入社。システム部を皮切りに、コールセンター、経営企画室、営業部、製造部と幅広い業務を経験。社内システム開発や顧客情報管理、POS・ERPの導入、原価管理などに携わり、事業の成長に貢献。製造部異動をきっかけにISO22000(食品安全マネジメント)やISO14000(環境マネジメント)に関心を持ち、2016年からISO認証機関に在籍出向。2020年にISO9000主任審査員、2022年にISO22000主任審査員、FSSC22000審査員資格を取得。辛子明太子の品質向上に尽力する中で、塩蔵(一時加工)の重要性を再認識し、改善を提案。前社長退任を契機にふくやの子会社である株式会社ヤマトバイオレッツの経営を任され、社長に就任。現在は、長年の経験を活かし、食品製造の品質向上と業界の発展に尽力している。
企業情報
株式会社ヤマトバイオレッツ
■TEL: 092-584-7755
■住所:福岡県大野城市仲畑1-6-1 [MAP]
■HP: https://yamatobioletz.co.jp/

